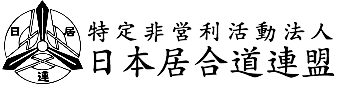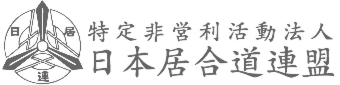無外眞伝無外流とは
無外流の歴史
 流 祖 辻 月 丹 資 茂 流祖 辻月丹資茂は、近江源氏の佐々木高綱の末流で辻弥太夫の二男として慶安二年近江国甲賀郡宮村馬杉において誕生した。
流 祖 辻 月 丹 資 茂 流祖 辻月丹資茂は、近江源氏の佐々木高綱の末流で辻弥太夫の二男として慶安二年近江国甲賀郡宮村馬杉において誕生した。
幼名は兵内といい剣術に志ざし、寛文元年に京都へ出て山口流の山口卜真斎に13歳で入門して足掛け14年、26歳にして師匠から免許を許された。
その後江戸に行って麹町に道場を構え、精神修養のため麻布の吸江寺(現在は渋谷区)の石潭禅師の許に通ったが、延宝8年の32歳のときに禅師は遷化された。引き続いて第2世の神州和尚について参禅し、45歳の時に開悟した。
神州和尚は石潭禅師の名によって次の偈を与えた。
一法実無外
乾坤得一貞
吹毛方納密
動着則光清
以来、月丹資茂と名乗り流名を無外流とした。
弟子には、小笠原長重、酒井忠挙、山内豊昌等の大名を始め、1万石以上は32名、直参の士150名、陪臣の士932名と記録されている。
享保12年6月23日に79歳で歿した。芝高輪の如来寺(現在は品川区)に葬られた。
無外子一法居士
主に土佐藩(山内家)、姫路藩(酒井家)に伝承された。
無外流居合は正確にいえば自鏡流居合です。姫路藩においても正式の場合は「自鏡流居合」と称していましたが、無外流剣術の指南役が指導するため、一般には無外流居合と称していました。辻月丹は自鏡流居合を学び、代々自鏡流宗家の指導を受け、姫路藩の高橋八助充亮と高橋達蔵充玄は自鏡流居合5代の山村司昌茂に学んで免許を受けました。高橋八助成行も自鏡流6代山川弥平能豪に学び高橋家に受け継がれました。
系譜
流祖 辻月丹資茂(江戸)
二代 辻右平太(江戸)
三代 都治記摩多資英(江戸)
四代 都治文左衛門資賢(江戸)
五代 都治記摩多資幸(江戸)
六代 高橋八助充亮(姫路藩)
七代 高橋達蔵充玄(姫路藩)
八代 高橋八助成行(姫路藩)
九代 高橋哲夫武成(姫路藩)
十代 高橋赳太郎高運(大日本武徳会)
十一代 中川申一士龍(日本居合道連盟)
特徴
簡潔な運剣と体捌きを主とした業と所作が特徴です。
現在の活動
各支部道場での稽古の他、特別稽古会、合宿、宗家による直接稽古など
国内道場は、大阪府、奈良県、兵庫県